

208.⑯The end(~her majesty209⑰~her majesty×KoToDaMa(音楽と言霊)
ついにBeatles古代文字、最後の曲となりました。 バンド、うた、音楽と言霊のARTいかがでしたでしょうか? このデモトラックのような書は、いずれ一冊のソングブックとして出版したい! ステキな出版社ㇺ!それでは、また会う日まで! 208.⑯The end(~her...


207⑮Carry that weight(傳 伝えるということ)×KoToDaMa(音楽と言霊)
207⑮Carry that weight重荷 傳 伝えるということ(傳)<水分意訳ポエム> 荷物、何、疑うの その思い 重荷 ず ぅつと背負っていくことにしたんだね 文字解説 常【伝】6画 (傳)13画 2524 [字音]デン [字訓]つたえる・おくる・うつす 説文■...


206⑭Golden slumbers(子守唄)×KoToDaMa(音楽と言霊)
206⑭Golden slumbersララバイ嘗ての道(子守唄)<水分意訳ポエム> さぁおやすみ。そんなに泣かないで。 これがお気に入りの子守唄だよ すばらしい眠りのために まぶたが満、かつての微睡(まどろみ) ほほえみながら目覚めよう かつて道があった...


205⑬She came in through the bathroom window(窓)×KoToDaMa(音楽と言霊)
205⑬She came in through the bathroom window(窓)<水分意訳ポエム> 彼女はバスルームの窓から飛び込んできた。 優雅な登場さ。ダンサーだったらしい。 サンディはマンディに電話したって! ぼくにはツチュゥーズデイから連絡あったよ!...

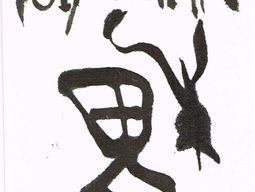
204⑫Polythene Pam(魅)×KoToDaMa(音楽と言霊)
204⑫Polythene PamSMの魅力)<水分意訳ポエム> ポリシーン パン 一見の価値アリ! すごい美人、まるで男 みたいに見えるんだ M 魅力的な身体 ボーイッシュ ああ、S 伸び盛りの木々。 魅 文字解説 常【魅】15 [■]13[音]ミ [訓]もののけ・すだま...


203.⑪Mean Mr.Mustard(老人)×KoToDaMa(音楽と言霊)
203.⑪Mean Mr.Mustard(老人)<水分意訳ポエム> 哀れなマスタード爺さん。公園で眠る。孫たちは働く。 、とある日。。。 陛下に一目合おうと出かけたとき 興奮してののしり続けたのは、薄汚れた爺 ああ老人 ああ老人とは? 文字解説 【老】6画 ...


202.⑩Sun king(Lennon(日立)×KoToDaMa(音楽と言霊)
202.⑩Sun king(Lennon )<水分意訳ポエム> 太陽の王様がやってきた! みんな笑ってる みんな幸せ ああ 太陽の王様だ! 文字解説 【昊】8画 6043 [■]9画 6022 [■]15画 2664 [字音]コウ(カウ) [字訓]そら 説文■ 金文■...


201,⑨You never give me your money(魔の法)×KoToDaMa(音楽と言霊)
201,⑨You never give me your money交渉 魔法 )<水分意訳ポエム> それは魔法か? いくあてのない おかねもない 1,2,3,4,5,6,7, いい子はみんな天国行くけどね 文字解説 常【魔】21画 0021 (■)21画 0021 ...


200、⑧Because(故に)×KoToDaMa(音楽と言霊)
200、⑧Because丸い強い青い 古 (故に)<水分意訳ポエム> なぜなら、一番古くて、いちばん新しいものだから。 地球はまるいから 風は強いから 空は青いから いにしえより 未来より 愛はきみ きみは愛 ぼくらは巡り巡って 故に...


199.⑦Here comes the sun(Harrison) (日)×KoToDaMa(音楽と言霊)
199.⑦Here comes the sun(Harrison) ()<水分意訳ポエム> 太陽が顔を出す ぼくも顔を出す笑 大丈夫さ! 文字解説 常【日】4画 6010[字音]ニチ・ジツ [字訓]ひ・ひる・ひかり・さきに説文■...







![申考2 亡くしたもの。失ったもの。[倒木祭祀]](https://static.wixstatic.com/media/b1627a_2e86f9df6c7248ebb6389cfed2a7e81d~mv2.jpg/v1/fill/w_318,h_178,fp_0.50_0.50,lg_1,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/b1627a_2e86f9df6c7248ebb6389cfed2a7e81d~mv2.webp)
![申考2 亡くしたもの。失ったもの。[倒木祭祀]](https://static.wixstatic.com/media/b1627a_2e86f9df6c7248ebb6389cfed2a7e81d~mv2.jpg/v1/fill/w_220,h_123,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/b1627a_2e86f9df6c7248ebb6389cfed2a7e81d~mv2.webp)


































